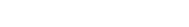協働パートナー:「神田藍愛〜I love KANDA〜 プロジェクト」に参加する企業・団体・住民の皆様
ダンクソフト本社のある東京都千代田区の神田エリアには、その昔、染物屋の集まる日本有数の「紺屋町」があった。全国の藍や問屋が集まり、いろいろな地域同士を藍で結んでいた場所だ。2020年12月、この神田エリアで、有志を中心に「神田藍プロジェクト」が誕生した。神田にゆかりのある「藍」を媒介とし、地域で暮らす人々や働く人たちによるコミュニティをつくろうと、小さくはじまった「神田藍愛〜I love KANDA〜 プロジェクト」(以下、神田藍プロジェクト)が今、急速な展開を見せている。
■藍を媒介に地域がつながる「神田藍プロジェクト」がスタート
神田藍プロジェクトのメンバー
後列左から
2番目 東京楠堂 井上智雄氏
4番目 株式会社ハゴロモ 伊藤純一氏
5番目 一般社団法人 遊心 峯岸由美子氏
6番目 ダンクソフト 代表取締役 星野晃一郎
神田藍プロジェクトでイニシアチブをとるメンバーのひとりが、一般社団法人 遊心 代表理事の峯岸由美子氏だ。遊心は、「自然・家族・仲間が共にいる喜びを通して、どのような環境においても『しなやかに自律する』人を育てること」を理念に掲げ、都市部の自然をテーマに、親子や子供を対象としたワークショップの実績が豊富な団体だ。
峯岸氏は以前、神田に本社を持つ株式会社ハゴロモのビルをフィールドに、伊藤純一 社長(当時)とともに、地域の子供たちと屋上で野菜を育てるプロジェクトを実施していた。しかし実際には、日差しが強すぎることによる水不足など、野菜を育てるには厳しい環境だった。そこで、都心のビル街という環境にも強いであろう「藍」を育てるのが面白いのでは、というアイディアが生まれ、これが神田藍プロジェクトへと形を変えていったのだ。
■「地域コミュニティの活性化」が「防災」につながる
一方、40年にわたり都心にオフィスを構えるダンクソフトには、もともと「防災」への課題意識があった
ダンクソフトが考えるこれからの防災についてはこちらのコラムをご覧ください。https://www.dunksoft.com/message/2022-06
巨大地震などの災害時に、企業に求められるのは迅速なリカバリーである。ダンクソフトでは2008年からテレワークの実証実験をするなど、デジタル環境の整備は進み、BCP対策は万全だ。だが、防災を考える時、もうひとつの要となる「地域コミュニティとの連携」は、希薄な状態だった。
ちょうど本社を神田駅前の新築ビルに移転後、ほどなくして、神田藍プロジェクトの話が舞い込んだ。それは、神田に住む人、働く人、愛する人たちが共に力をあわせ、神田をより楽しく、心地よく過ごせる街へと育てることを目指して、神田のシンボルとなるだろう「藍」をみんなで育てる活動だった。
移転したばかりで、地域とのつながりを求めていたダンクソフトにとって、神田藍プロジェクトは渡りに船だった。このプロジェクトを通じて、地域コミュニティや地域企業との新たな結びつきが生まれ、将来的には神田エリアの防災にもつながる可能性がある。そこで、2021年12月、ダンクソフトは迷うことなく参加し、事務局メンバーにも加わった。
■デジタル企業が植物を育てるという試み
植物や自然に精通している峯岸氏いわく、神田藍プロジェクトは、最初の1年は試行錯誤の連続だった。思ったように藍がうまく育たない場所があったり、企業や地域の方々にもなかなか理解を得られないなど、色々な課題が出ていた。峯岸氏は、これらの課題へひとつひとつに丁寧に対応していくことで、様々な方たちがプロジェクトへ参加しやすい状況をつくる工夫を重ねた。
藍の育て方を紹介する動画「種まき編」。他にも、「植替え」「間引き」「水やり」などを紹介した動画もあります。
藍の育て方を動画でシェアしたり、藍を育てる方たちを訪ねてよく話をしながら、藍を育てることがコミュニティの活性化につながるという未来の物語を、粘り強く語りつづけていた。
ダンクソフトでも、その未来の物語に賛同し、いち参加企業として、藍の鉢植えを1つベランダで育てることから1年目が始まった。コロナ禍となり、全社在宅勤務となったオフィスのベランダで、藍は元気に育っていた。オフィスに出社していたダンクソフト代表の星野は、在宅勤務する全国のスタッフたちへ、藍の様子を共有した。また毎日の水やりをする中で、育成プロセスをデジタル化することを試みた。ウェブカメラを設置し、24時間どこからでも藍の様子が見られるように簡易なシステムをつくり、自動で藍が水を吸い上げる装置を入れるなど、藍が育つ環境をデジタルを使って整えた。
■多様性から広がる神田藍コミュニティ
メンバーたちの活動の様子を見て、徐々に徐々に神田藍プロジェクトの輪は広がっていく。神田明神の境内にも藍が育ち、美容院や酒問屋の軒先にも藍のポットが置かれ、藍をめぐる会話が街に増えはじめた。興産信用金庫や神田学会などの企業・団体も、この新しい動きに関心を寄せて、協力・連携が生まれはじめた。
そんななか、東京楠堂の井上智雄氏が参加することになり、神田藍プロジェクトに大きな変化が起こりはじめる。楠堂さんといえば、和本や集印帳などの製造販売をする神田の老舗企業である。地域とのつながりも強い。
自治会とのつながりを持つ井上氏が起点となり、2022年春には神田東松下町の町内会とプロジェクト・メンバーが対話する機会が生まれた。これをきっかけに、5月の子供の日にあわせて、地域の子どもたちへ160個もの藍の種を育てる牛乳パックの鉢植えを配布するイベント実施が決まった。続いて、8月20日には、各自で育てた藍の葉を持ち寄って、叩き染めをするイベントを開催。「自分で育てた藍の葉で布を染める」という初めてだらけの体験は、参加者から大変好評を得た。「藍」を媒介に多様な属性の人々が偶発的に集まり、今までにない神田藍コミュニティが、さらに広がりはじめている。
■「WeARee!」と「ダイアログ・スペース」で活性化する地域コミュニティ
ダンクソフトでは、神田藍プロジェクトのなかで、デジタルを活用した2つのことを提供している。
ひとつ目は「WeARee!」(ウィアリー)を活用したウェブサイトである。WeARee!とは、バーチャルツアーやARカメラを使ったコミュニティ・イベントを誰でもカンタンにつくれるウェブ・ツールだ。
すでに遊心は、2020年に WeARee!を活用し、ダンクソフトと協働プロジェクトを行っている。今回の神田藍プロジェクトでは、WeARee!の機能の一部である「ウェブサイト機能」と「写真投稿&チャット機能」が生かされている。藍の写真を自由に投稿できるオリジナル・ウェブページを制作。会員専用ページでは、メンバーが投稿した写真について、チャット機能でメンバー同士が対話をすることができる。藍の発育状態が良くない時に写真を投稿すれば、メンバーからアドバイスが自然と届く。オンライン上で場所や時間を選ばず交流できるコ・ラーニング(Co-learning/共同学習)のコミュニティが、WeARee!上に誕生している。
WeARee!を使った、神田藍プロジェクトのページ
https://yushin.wearee.jp/kanda-ai
遊心とダンクソフトの協働プログラムの事例紹介はこちら
https://www.dunksoft.com/message/yushin
「神田藍プロジェクトに関わる方には、ご高齢の方もいます。実際に運用してみると、そもそもWeARee!にログインできないという声も出ました。ダンクソフトさんに相談すると、従来型のログイン方法にとらわれない、使いやすいシステムに作り直してくださいました。神田のメンバーのみなさんと対話をしながら、ダンクソフトさんと協働して、より使いやすいUIづくりができて助かっています」と、峯岸氏は語る。
ダンクソフトのダイアログ・スペースに集まる神田藍プロジェクトのメンバー。
ふたつ目は、ダンクソフトのオフィス内にある「ダイアログ・スペース」の活用である。 この「ダイアログ・スペース」は、オンラインとオフラインのハイブリッド型ダイアログにも対応した、良質な対話空間だ。社外のイベントや会議にも多く利用されており、神田藍プロジェクトもこのダイアログ・スペースで集まることが多い。
また、オフィスにはアイランド・キッチンが備わっているため、ちょっとした生葉染めも、このスペースですることができる。メンバーそれぞれが、自分で育てた藍の葉を持ち寄って、ダンクソフト代表である星野と共に、わきあいあいと生葉染めを楽しむ場面も増えてきた。
■「藍×デジタル」で育まれる神田藍コミュニティ
ダンクソフトの社内でも、神田藍プロジェクトを通じて、予想外の効果が生まれた。それは、神田地域を越え、全国で働くダンクソフトのスタッフのあいだに「藍」を媒介にした交流が活性化したことだ。
2022年春、徳島サテライト・オフィスのメンバーが揃って神田オフィスに訪れた際に、神田で育てた藍の種を持ち帰った。東京で育てた藍が、神田を離れ、徳島でも花を咲かせたのである。東京・徳島間のオンライン・ミーティングでは、当然のように「藍」が話題にあがり、自然と対話も活性化していく。先日は、東京と徳島合同で、生葉染めのオンライン体験を行ってみた。他にも、栃木や江ノ島に住むスタッフたちも苗を持ちかえり、藍をそれぞれの地域で育てている。今や「神田藍」は、既に神田エリアにとらわれない、様々な人々のコミュニティを結ぶ「媒介」となった。
東京楠堂の井上氏は、「ゆくゆくは育てた藍を使った自社ブランドをつくりたい。また体験型の藍染ワークショップなども視野に入れていきたい。」と、神田藍を活かした新しいビジネスの可能性に胸を膨らませている。遊心の峯岸氏も「コロナが落ち着いたらWeARee!のARの機能を活用した、オンライン・オフラインのハイブリッドなイベントを企画したい」と期待を語る。
「20年後、自分で藍染めした法被を着た若者たちが、神田祭で練り歩く」。これは、神田藍プロジェクトが描く、ひとつの未来の物語である。「藍×デジタル」を活かした神田藍プロジェクトは、これからも、神田地域の「ソーシャル・キャピタル」を豊かに醸成する新しいコミュニティとして育っていくことだろう。
■導入テクノロジー
WeARee!
ダイアログ・スペース(ダンクソフト内)
■神田藍愛〜I love KANDA〜とは
神田に住む人、働く人、愛する人達が共に力を併せ、神田をより楽しく、心地よく過ごせる街へと育てるためのプロジェクト(運営:一般社団法人遊心)。藍を新たな街のシンボルとし、神田の名産として様々な商品やサービスを 提供・発信する仕組みづくりを行う。一連の活動は持続可能な地域づくりの基盤となり、また人と人、人と地域の絆を深める結び目となることを目的としている。