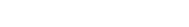ダンソフト40周年企画のひとつとして、2022年から、社内で「未来の物語」を描くプロジェクトを実施してきました。2023年1月に集まった物語は、全部で実に20作品にのぼります。これらを読み合い投票する社内コンテストを行いました。今回は、受賞者4名とプロジェクト担当者を迎えて、今回のプロジェクト、そして、この先の未来について語り合いました。
最優秀賞 野田周子(ウェブチーム)
役員賞(板林賞) 大川慶一(企画チーム)
役員賞(渡辺賞) 濱口航貴(ウェブチーム)
役員賞(星野賞) 港左匡(開発チーム)
プロジェクト担当 澤口泰丞(開発チーム)
代表取締役 星野晃一郎
▎ダンク史上初の快挙、“こんな経験は40年間で初めてだ”
星野 何度か話していますが、最初は有志数名だけで物語を書くことになるかと予想していたんです。それが、澤口さんの「いや、全員で書くんだ」という発言から、全社プロジェクトになっていきました。しかし、ここまでになるとは思ってなかったですね。
澤口 会社の未来を考える時に、一部の人だけが考えた未来に乗っかるような状況ってすごく怖いなと、まず思ったんです。そうならないために、一人ひとりみんなが会社の明るい未来を考えてもらいたい。そのためのきっかけになるという意味で、物語を書いて未来を語るという今回のプロジェクトは、意義のあることだったと思います。
星野 こうして未来語りの物語をお互いに交換し、物語を介してお互いを深く知ることができたというのは、チームとして相当頼もしいですよ。ひとつ言えるのは、ダンクソフト40年の歴史の中で、社内の人たちがこれだけお互いを知ったのは初めてだということです。こんな経験は私もしたことがなく、ダンク史上初の快挙です。ここからチームがどうなっていけるか、40周年を迎える7月に向けて、すごく楽しみにしています。
澤口 私自身、何度も感動することの連続でした。まずやはり20作品ができあがったこと自体が嬉しく感動的でしたし、読み込んでみると、一つひとつが本当に素敵で、また感動しました。さらに、賞を選ぶ投票の段階でも、多くのスタッフが投票に参加してくれたことにも感動しましたし、かつ投票に添えられたメッセージにも感激しました。
代表取締役 星野晃一郎
星野 ここまでの数が集まるとはね。年末の仕事納めの時点で見たときは8本だったんです。ところが、1月4日の仕事始めの日に開けてみたら、いきなり20本が提出されていて。すごいですよね、これって。
澤口 最初は最優秀賞ひとつだけの予定でしたが、「これだけの数が集まったし、しかも力作揃いで、賞がひとつだけではもったいない」ということになり、急きょ役員賞を追加してもらいましたね。ダンクソフトには役員が3人いるので、新たに賞が3つ増えて4つになりました。今日は受賞者の皆さん4人に集まってもらいました。
▎未来社会を描く難しさ。ここから VR の未来はどうなる?
──まずは今回の最年少受賞者の濱口さんです。徳島県の阿南高専を2022年に卒業し、春に新卒入社してまもなく1年。今回、役員賞(副社長・渡辺賞)を受賞しました。
濱口航貴(ウェブチーム)
濱口 私の物語は、中学時代に初めてスマートフォンに触れて、文明的なものを感じたエピソードから、やや SF 的ともいえる未来社会へと向かう、という内容でした。中学時代、家ではスマホを持たせてもらえなくて、親に内緒でスマホを入手しました。初めて文明に触れた経験でした。徳島という田舎で生まれ育って、それまで家と学校の往復だけが世界だったんです。だから、スマホとの出会いはすごい衝撃でした。初めて都会の人たちと同じ情報に触れ、同じものを享受できたという感覚です。これがIT分野と出会った原体験となって、今の自分があることを物語に書きました。
星野 濱口さんのその興奮はわかる気がしますね。私が初めてインターネットを体験したのが、たしか1993年頃。当時はニフティー・サーブの時代で、あの頃のブラウザは、たしかモザイクだったかな。世界に窓が開いた興奮を、よく覚えています。
濱口 スマホ以前は何も持っていなかったので、逆に感動が大きかったかもしれません。それまで情報を得るといえばテレビぐらいしかなかったところから、いきなりインターネットに触れたので。
星野 濱口さんが出会ったスマホですから、相当完成された状態のデジタルを、最初にいきなり見たわけだからね。
濱口 はい。僕の物語の結末は、未来社会がどうなっているかを思いつくまま書いたものでした。その世界では、VRやアバターを当たり前に使って仕事をしている想定です。ただ、個人的には、実際にはこの方向でVR が進化することはないだろうと思っていて、そう思いながら書いたところがあります。
というのも、未来の姿がまだ想像がつかなくて。今のVRは、VRゴーグルをつけて3Dでモデリングされた世界を目視することができるものです。でも、まだその空間で移動する方法が明確に定義されていない感覚があります。いわゆるゲームでいうところのコントローラーができる前のような状態なんじゃないかと思っています。
なので、その VR 空間でどういうふうに立ち回るかが確立されてみないことには、実際にどのように実用されていくのかが思い描けなくて。仕事でコミュニケーション・ツールとして使うなら、VR ゴーグルをつけて何かするよりも、現在のビデオ会議の方が効率的です。どういうところで VR がビデオ会議を上回るのか。離れたもの同士が会議をしているというような方向性ではないんじゃないかと思いつつ、あえてフィクションとして書いてみた、という感じです。
澤口 今回、「ダンクソフトの未来像」をみんなで考えていくにあたって、一人ひとりの未来が合わさったものが会社の未来になっていってほしいと考えました。みんな苦労しながらも、会社と自分の「未来」について、すごく考えて書いてくれましたね。
濱口 物語を書く上で困ったのは、まさに未来の部分でした。実は色々な未来シナリオを書いて、何回も書き直してみたんです。でも、何度書いても「これは違うな」という未来しか書けず、それで「こうはならないな」と思う未来を描くことになってしまいました。今回の僕の物語の反省点はそこで、つくりたい未来像を描き切れなかったことでした。
物語を書いてよかったことは、自分が過去に歩んできた道をあらためて振り返るきっかけになったことと、未来について考えられたことです。日頃はやはり、どうしても目の前のことに集中することが多いので、改めて先の事を考えるよいチャンスになりました。今回は、つくりたい未来について書ききれませんでしたが、引き続き、もっともだと思える未来像を書けるようになっていきたいです。
大川 濱口さんも港さんもすごく若くて、自分とは離れた世代の若者です。そういう方たちがどういう視点で物事を見て、どういう経験をしてきたのかを、今回、物語を通して詳しく知ることができました。率直な感想として、共感しました。そこに書かれていた子供時代のときめきや行動原理は、私自身も同じ年頃の頃に感じていたものと近く、親近感を持ちました。
▎過去の延長ではなく、そうあってほしい未来を描く
──続いて、濱口さんと同時入社、同じく阿南高専出身の港さんです。役員賞(社長:星野賞)を受賞しました。
港左匡(開発チーム)
港 私の物語は、自分の過去の経歴をたどり、今後どうなっていってほしいかという未来について書いたものです。前半の振り返りパートは、高専に入った頃の話からダンクソフトに入って仕事をしている現在あたりまで。後半は、未来ということで、まあ、好き勝手に書きました(笑)。私も濱口さんと同じで、未来で自分が具体的に何をしているかを書くのは難しかったので、未来がどうあってほしいかを想定して、どう働いているかの観点で書きました。
内容としては、メタバース的な社会の姿を、「なるべくそうあってほしい」という観点で書きました。バーチャル空間というか、デジタル技術を使った働き方が標準になっていってほしいということですね。また、そのなかで、ダンクソフトは新しい技術をどんどん取り入れていく積極的な姿勢をいつまでも保ったままの企業であってほしい、というようなメッセージを書きました。
ただ、僕もこのままではメタバース空間で仕事はできないと思っています。具体的には、入力デバイスが、現状のキーボードやタッチ・ディスプレイなどのままではダメで。濱口さんの話にもゲーム・コントローラーの話が出ていましたが、もっと根本的にひっくり返すような何かがないと、このままでは使いづらいです。それをどう解決できるのかというと、ひとつは軽量化ですね。今のヘッドフォンくらい身軽なもので、VR空間に入っていかれるぐらいの軽さが欲しい。現状だと、トラッキング・センサーなど大掛かりな装置が必要なことが、今の技術的限界なので、今後それがどうなるか。うーん、わかりません(笑)。
星野 港さんが書いた物語を初めて読んだのは、私と入江さんなんですよ。去年の全社会議でチームが同じだったんですね。そのときにみんなで物語を書き始めたわけですが、これは面白いなと思いました。だって港さんの物語なのに「私は竹内祐介です」から始まるんですよ。もうその時点で実際にイメージも浮かぶし、何が始まるんだろうと先が期待されて。その書き出しがよかったのと、全体の構成も構造的で、そこも良かったです。
港 物語の始まりは会話で書いた方が良いというのを聞いたことがあったので、自分としては特殊なことをしたつもりはなかったんですが(笑)。
書いてみてよかったのは、よい振り返りの機会になったことです。過去の自分は、ある意味で他人だと思うので、そういう意味では、書く方も読む方も含めて、他者の経歴を知る、とても良い経験になりました。
苦しかったのは、過去の厳しかった経験と向き合うことでした。結局、辛いことばかり書いても仕方ないと考えて、ばっさりカットしました。あと、書く内容や構想自体は頭の中でイメージできても、それを実際に文章に起こすことに時間がかかり、なかなか難しかったです。今後推敲していくとしたら、未来の部分で自分が何をしているかを膨らませると、もっとバランスがよくなっていくかなと考えています。
野田 高専に進学する人は、中学の時点ですでに将来を考えて、高専という5年の道を選んでいるだけあり、港さんも濱口さんも、未来社会の姿をよく描けていましたよね。普段の仕事ではチームが違うのですが、松江のワーケーションに参加したとき、松江と徳島をオンラインでつないで、おふたりのプレゼンを聞く機会がありました。こうして物語を読ませてもらったりして、ふたりともプレゼンも文章もうまく、吸収力と行動力のある方たちであることがよくわかります。
大川 私も普段はチームが違うので関わりが少ないのですが、こうして物語を通しておふたりの経験や思いを詳しく知ることができてよかったです。皆さんの物語を読んでいると、港さんも濱口さんも野田さんも、ダンクソフトに今こうしてみんながいることが、奇跡的だなと感じました。
▎心に抱えた歯がゆさが、物語をつくることで昇華された
──次は、最後の役員賞(取締役:板林賞)、大川さんです。
大川慶一(企画チーム)
大川 昨年5月に祖母が亡くなりました。私はそこを起点とする物語を書きました。享年99歳、あと1年で100歳だったのですが。昨年はコロナ禍まっただなかだったので、祖母が倒れて入院したと聞いて病院に行っても、直接には会えません。リモート面会しかできないんですね。そのまま何ヶ月か通い続けたのですが、ずっとリモート面会のまま。結局、祖母は最後まで、画面越しに映る私たちを家族として認識できませんでした。こちらが言葉をかけても、伝わっているという実感も、励ませているという手応えもなく、歯がゆい思いをしているうちに亡くなってしまいました。
これまでダンクソフトで、リモートワークや年配の方々のデジタル・ワークをサポートする仕事をしていたにもかかわらず、灯台下暗しで、一番身近な家族に対してケアができていなかった葛藤がありました。そこから、未来につなげていきました。世の中的にも、世代がひとつ上がると、もう見えない領域というか、手付かずのまま問題が置き去りにされていることに気づき、これまでITに触れる機会のなかった高齢者に何かアプローチできないかと考え、行動を起こしていく、というのが物語の流れです。
最終的には、高齢者施設で、IT機器をつかったコミュニケーションやレクリエーション、またタブレットで絵を描くとか、ツールに慣れる機会を高齢の方々へ提供する事業を進めている未来を、フィクションとして描いた物語となりました。
星野 物語の構造のひとつに、「不足から充足に向かう」ということがあります。大川さんの物語は、ご自身にとって身近な課題、つまり不足からはじめて、それが充足された未来のビジネス・プランを構想したことが、とてもよかったですね。
大川 理想の未来を書くことで、心の中に抱えていた歯がゆさやモヤモヤが、ある程度は解消されたように感じます。このモヤモヤは、自分の中に抱えたままだと、ずっと悔いとして解決されずに残るたぐいのものだったと思うので、文字にして出力できて、本当によかったです。
港さんは辛い経験を振り返ることが苦しかった、と話していましたが、私はそこには難しさはなかったです。むしろ逆でした。祖母が亡くなった時、亡くなる瞬間に立ち会えなかったこともあって、全く何の感情も浮かんで来なかったんですよ。それが、具体的に物語として表現したことで、ああ、こういう気持ちを発散したかったんだな、という気持ちに、ようやく気づくことができました。
港 いろんな世代がデジタル・ツールを使えるようにしようという、「デジタル・デバイドの解消」に向かうビジョンが感じられて、とても共感しました。実は私が投票したひとつが、大川さんの物語だったということを、ここで告白します(笑)。
野田 私もコロナ禍のなかで家族が入院し、面会もできなくなっていく体験をしたので、重なる部分があり、共感をもって読みました。また、高齢者のデジタル・デバイドの現状と、課題解決のための事業提案の必要性が、とても切実な問題として迫ってきました。大川さんの試みが、今後も多くの人に役立つと良いなと思いました。
星野 大川さんの言うように、物語として書き出すことで越えられたり、逆に港さんの言うように、一度書き出してみて思い切って捨ててしまうというのも、ひとつの物語効果だと思います。やはり自分を外に表現するのは大事ですね。今回のことは、それぞれの人が自分自身を振り返り、次を考える、いい機会になりましたね。
澤口 はい。今回、皆さんに物語を書いてもらいたかったねらいの一つとして、お互いのことを知ってもらうということがありました。コロナでテレワーク化が進み、ずっと離れて仕事をしていて、お互いのことが見えづらい状況が続いていました。ですので、同僚を知るためのツールとしての物語ということも、意識していました。物語づくりは、各自が自分や他者に向き合うことでもあり、過去、現在を超えて、未来に向けてこれからどうしていくかを考えることでもあります。このあたりがやはり、物語プロジェクトとして、とても有効だったのではないかと思います。
▎「偶発性」から始まる、私の物語
──それではいよいよ最後、最優秀賞の野田さんです。
野田周子(ウェブチーム)
野田 私も基本的には自分の経歴を物語化しました。物語は、私が松江に行ったこと自体が、家族の遺したメッセージとシンクロしていたという偶発性を発端として始まります。そして、人とのご縁や偶発的な出来事がダンクソフトへの入社につながっていったこと。去年、松江でのワーケーションを経験したんですが、その経験やその周りに起きた偶然の出来事を描いた物語でした。
例えば、転職時に私を面接した人が同じ小学校だったことが、何十年後かにわかったことや、ワーケーション先の松江で、出向先の企業で仲の良かった出雲出身の方が、実はダンクのメンバーとご近所同士で親しくしているのがわかったこととか。ダンクソフトでは日本全国どこでも仕事ができるので、それが将来は世界に広がっていくという物語になりました。
大川 野田さんの物語は、ここまで多様な経験をされていること、そしてそれをここまで詳しく物語にされていることがすごいと思いました。なんといっても文章がすばらしくて、めまぐるしくシーンが動くんですね。松江に行くところから始まって、綱渡りのように進んで、最後は奇跡的なめぐりあわせでダンクソフトにたどり着く。とてもドラマチックで面白かったです。
野田 ありがとうございます。物語を書いてよかったことは、何度も皆さんからも話が出ているように、やはり、これまでを振り返ることができたことでした。あんなことがあったな、こんなこともあったな、と懐かしさを感じながら、ダンクソフトで働いている現在までの出来事を辿ることができたのはいい経験でした。
ただ、私は未来については描けなかったんですよ。大川さんも港さんも濱口さんも、未来が書けていて、すごいと思いました。私の場合は、目の前の現実的なことしか考えられなくて、なかなかそこまでいきませんでした。でも、未来もしっかり考えなきゃいけないなというのが、これからの課題だと分かったことも、今回参加した収穫でした。
星野 実は、私も票を入れました。野田さんはダンクソフトに来る前は旅行関係の仕事をしていて、世界各地を旅行しています。多彩な経験のなかで、いろんなことに挑戦してきた、ものすごいチャレンジャーの物語でした。仕事が大変なときにはバスケットボールをするのが息抜きだという部分などは、私もテニスをしているので、共感しましたね。
今回、4人の物語以外も含めて、どの物語も、ボリュームも構成力もよく、読み応えのある物語ばかりでした。ですが、その中でも野田さんの物語は、多くのスタッフからの票を得ることになりましたね。
▎新しいことへの挑戦が評価されるダンクソフト
星野 今回、澤口さんがいろいろと工夫して主体的に動き、新しいプロジェクトを、ここまでに育ててくれたことは、これからのモデルになると考えています。異なるものやひとのあいだを結び、展開をつくる「インターミディエイター」を、実践したプロジェクトになりましたね。通常の開発者としての業務もあるなか大変だったと思いますが、よくやってくれました。それはきっと誰もが感じていることではないでしょうか。
野田 まったくそう思います。それに、人望のある人でないと、一緒になにかをつくりあげようとは思えないので、そういった面で澤口さんは適任だったと思います。今後もし何か手伝えることがあるなら私も参加できたらと思うので、ぜひ声をかけてください。
濱口 実はプロジェクトの途中の段階で、澤口さんが僕や港さんを含む数人を集めて、意見交換の場を設けてくれたことがありました。そんなふうに若い世代の声も聞きながら、もちろん他にもいろんな人の意見を聞きながら、プロジェクトを進めていかれたのだろうと思うと、本当に感謝しています。
港 今回、こうして振り返りの機会をつくってもらえてありがたかったです。また、プロジェクトの進め方自体も素晴らしくて、多くの人に参加してもらう工夫をし、周囲の賛同を得ながらプロジェクトを推進していかれた推進力は、メタ的な観点でもすごいと思いました。他のプロジェクトにも応用できるポイントがいろいろあると思うので、どんな工夫をしたかを、ぜひ共有していただきたいです。
大川 今回、この物語プロジェクトで一番感謝しているのは、物語を交換しあうという形で、社内メンバーとのコミュニケーションができたことです。お互いの物語を読むと、どんどんその人の目線になって想像でき感情移入が進んで、人に対するリスペクトが生まれてくるんですよね。自己紹介やプロフィールの交換では、こうはなりません。すごく良かったです。
澤口 皆さんにそんなふうに評価してもらえて、担当した甲斐がありました。こういう取り組みは、通常のクライアント対応の仕事とは違うタイプのものですが、何か新しいことへの挑戦がこんなふうに評価されるというのは嬉しいですし、大事なことだと考えます。
▎会社自体がひとつの生命体
星野 ダンクソフトはもともと私が作った会社ではありません。私は社員番号4番で、4人目に入社したメンバーです。創業から今までに、約130人がこの会社に関わりました。その時その時に在籍した人たちが会社を支え、会社の40年をつくってきました。そう考えると、会社自体が、ひとつの「生命体」のようなところがあります。常に動き変化しながら、動的平衡を保って、イノベーションを起こし続けています。私は経営者ですが、私だけで作ってきたわけではないし、これからはそういう時代でもありません。
今後は、つくられた物語のひとつひとつを、孤立させずに、それぞれの物語を重ね合わせて、結び目をつくっていきたいものですね。さらに、社内メンバーだけではなく、パートナーやお客様も、物語に登場したり、自ら物語づくりに参加していただきたいと考えています。
デジタル・テクノロジーは、この40年で1億倍に成長してきました。この先、さらに進化は加速するでしょう。そこには、恩恵も危うさも、両方あるわけです。ですからそこに、どんなよりよい未来の物語を描けるかが、重要になります。だからこそ、これからはさらに、お客様とも一緒に物語をつくっていくのが必要だと考えています。そして、コ・ラーニングし、成長しあえる組織同士のネットワークが生まれていってほしい。これは私がもっている「コミュニティ」のイメージに通じるものです。お客様や社会と、共に進化、つまり「共進化」しながら、デジタルを使って、よりよい未来や社会がつくれるような流れができればと思っています。
今回の受賞者以外の、ダンクソフトにかかわる人たちが考える「未来の物語」を40周年記念特設サイトで公開しています。
https://www.dunksoft.com/40th-story