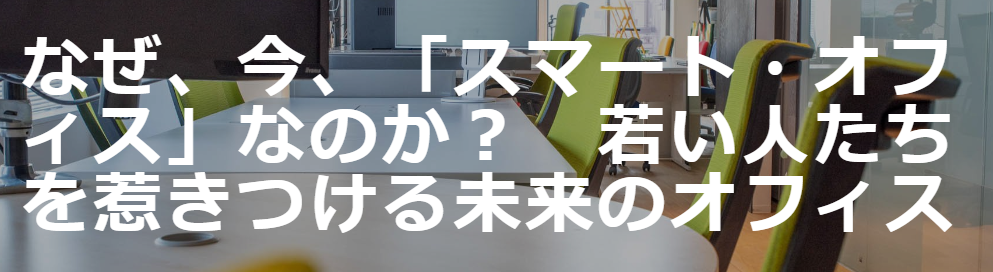いぶき福祉会は、岐阜市で重度の障害のある方々を中心に支援する社会福祉法人です。40年以上にわたりさまざまな活動に取り組み、昨年は法人化30周年を迎えられました。その節目の年に、いぶき福祉会とダンクソフトは、「親なき後問題」について、エンディングノート・プロジェクトのデジタル化に取り組みました。いぶき福祉会を代表するお二人をお招きして、そのプロジェクトの様子や、現場での課題など、福祉とデジタルの未来について語り合いました。
【左から】
社会福祉法人いぶき福祉会 業務執行理事 北川雄史さん
社会福祉法人いぶき福祉会 事務長/協働責任者 和田善行さん
株式会社ダンクソフト 代表取締役社長 星野晃一郎
もくじ
┃岐阜市をフィールドに、“仲間”たちとともに歩み続けるいぶき福祉会
┃「親なき後問題」。未来への不安に応えるエンディングノート・プロジェクト
┃親も交えた「開かれた場」で対話。プロジェクトが楽しく新鮮だった。
┃みんなで取り組んでいくコミュニティをつくっていくことが、次のステップ
┃岐阜市をフィールドに、“仲間”たちとともに歩み続けるいぶき福祉会
星野 まず始めに、いぶき福祉会についてご紹介いただけますか。今日は、事業全体の責任者である業務執行理事 北川雄史さんと、事務長/協働責任者である和田善行さんをお招きしました。
和田 いぶき福祉会は岐阜市で1994年に社会福祉法人として認可を受け、それ以前の歩みも含めるとすでに40年以上にわたって、障害のある人の支援を続けています。比較的、重度の障害のある方々とともに活動していることが特徴です。現在、日中に通って作業をしたり支援を受ける事業所が7つ、グループホームを3つ運営しており、あわせて150名弱の“仲間”が利用しています。私たちは障害のある利用者の人たちを日頃から“仲間”と呼んでいます。
北川 1980年代に、障害児・障害者を持つ親や関係者が集まり、共同作業所づくりから始まりました。私たちは、行き場所がなかった重度の障害のある人たちのためのコミュニティをつくりたかったんです。いまでこそ企業やNPOなど多様な組織がこうした課題に取り組んでいますが、当時は民間が社会福祉事業を行うことはできなかったんですよね。ですから、最初は無認可という形でのスタートでした。
和田 ちなみにいぶき福祉会は、岐阜市で初めて誕生した障害福祉分野の社会福祉法人でした。最初の施設建設にあたって必要な自己資金(建設費の1/4)のほとんどは市民からの募金でした。7千人から7千万円の寄付をいただきました。その後も計5回の募金を行い、活動に活かしています。
北川 私たちは、私立でも公立ではなく「市民立」という言葉をよく使っています。その分、運営はたいへんですけれど(笑)。
和田 いぶきでは、仲間たちと一緒にかりんとうやマドレーヌ、草木染めなどをつくっています。昨年、2024年7月のちょうど30周年の日に、事業所に併設された「ほとり」をオープンしました。ここは、商品を手に取って購入することができます。ですがそれよりも、マルシェやワークショップなど開催しながら、地域の子どもたちをはじめとした、たくさんの人たちと交流し、対話が生まれる空間として位置づけています。
北川 それまでは12年間、岐阜駅に直結した商業施設内に、「ねこの約束」というショップを持っていました。しかし、そこは面積も限られていたため、商品を置き、物を売るだけの場所になっていました。関係づくりを重視している私たちとしては、もう少し展開できる場所が必要でした。そこで、コロナ禍にいったんそのショップを閉じて、人々が集い、対話し、交流して、新しいものやことを生み出せる場所として再出発したんですよ。
星野 30年以上にもわたり、地域に開かれた福祉を実現されてきたのは、すばらしいことですね。昨年秋には、開発チームの竹内が、いぶきさんへ徳島から2回目の視察にうかがい、「ほとり」にも立ち寄らせていただいたと聞いています。
いぶき福祉会が2024年7月に新しくオープンしたショップ&地域交流拠点「ほとり」を見学
┃福祉の現場には、デジタルが寄与できることはたくさんある
星野 ところで、私と北川さんが初めて出会ってから、そろそろ10年になりますか?
北川 2016年の夏、日本財団CANPANが主催するNPOサマースクールからですね。私自身がその一コマを担当し、いぶきでの価値創造について、お話させていただいたんです。星野さんとは、その後の懇親会で初めて話した記憶があります。それがきっかけで星野さんも関わっていたインターミディエイターの講座に、私も参加したのが、その年の秋ですね。
和田 私が最初に星野さんにお会いしたのは2019年頃でしょうか。星野さんがやっているコミュニティ・ラジオの生番組に出演したのが最初でした。
星野 ちょうど岐阜の企業や団体と連携して実施する新しい社会貢献プロジェクト(Gifu Happy-Happy Project)を立ち上げるためのクラウド・ファンディングをされていたので、オンラインでお話しいただいたんですよね。
和田 星野さんはIT企業の社長さんだと聞いていたので、私はもっと堅い社長さんだと思っていて、すごく緊張していました(笑)。でもお話すると、とても和やかで柔らかいコミュニケーションをされる方で、安心した覚えがあります。
▶参考情報:ラジオ出演2回目(2020年12月8日) https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=427328628299664
(20:39~)
北川 その日、和田がラジオ出演させていただいた様子を、みんなで岐阜から見ていたんですよね。その様子を、Youtubeで公開していました(笑)。
星野 そうでしたか(笑)。そんな経緯があって、いぶき福祉会とダンクソフトがデジタル化で連携するようなことになりましたね。
和田 星野さんは、いぶき福祉会のことを知ってどんな印象を受けましたか?
星野 お二人の話を聞いたり、岐阜に足を運んだりしているうちに、障害福祉という大事なテーマの中で、デジタルの観点から寄与できるといいなと思いました。多様な人たちが明るく楽しく暮らせる社会づくりにデジタルで貢献することは、ダンクソフトの未来像でもあります。いぶきさんの活動と合致することがたくさんあると直感しましたね。
┃「親なき後問題」。未来への不安に応えるエンディングノート・プロジェクト
星野 今回、いぶき福祉会とダンクソフトの協働プロジェクトとして、「親なき後問題」に関わるエンディングノートのデジタル化をご一緒しました。
いぶき福祉会 業務執行理事 北川雄史さん
北川 なかなか知っていただく機会がないかと思うのですが、いわゆる高齢の方の介護は、前提として年老いた親を若い子どもが看るという構造です。ですが、障害のある方の場合は、老いていく親が、まだ若いけれども自分では生ききれないわが子を残していく構造です。兄弟などがいる場合、兄弟に託すことも昔ならあったのですが、今はなかなかそうもいかないという中で、では誰に託していくのか。その想いをどうやって伝えるのかということが、課題としてあります。
和田 自分がいなくなった後、わが子がどんな生活をするのか。どこで暮らすのか。財産の問題などもかかわってきます。「親なき後問題」は、30年以上前に私が大学生だったころにもあった問題で、今もあるテーマです。私たちのような団体は、そうした時にお子さんを託される先となります。
北川 この問題については、最近は、制度的にも整いつつあり、親が亡くなった後も暮らしていくことはできます。ですが、親としてはどこまでの情報を託してよいかなど悩むことがあります。たとえば、その子の好物がケーキだとしたら、ショートケーキではなくチョコレートケーキなのだとか、ジュースはオレンジよりもリンゴなのだとか、自分の思いを伝えられない障害者だからこそ、些細にみえても伝えておきたい大切なことが山ほどあります。
和田 そこで、解決の糸口として、親さんにエンディングノートを書き記してもらう取り組みが生まれています。この活動を、岐阜市のガバメント・クラウド・ファンディングの仕組みを利用して立ち上げたのが、プロジェクトの始まりです。
北川 親が「想い」を託していくために、エンディングノートは非常に有効な手段なんですね。クラウド・ファンディングを実施する際に、岐阜市が主催する公的なファンディングの仕組みを選択したのも、この課題を、社会課題として広く知っていただきたいという願いがありました。また、こうした悩みを持つ親や家庭、さらには関心のある人たちがつながれる、開かれたコミュニティをつくりたいと考えているからです。「親なき後問題」は誰にとっても身近な、「家庭の問題」であると同時に「社会の問題」です。
和田 ガバメント・クラウド・ファンディングは、今までに2回実施しています。1回目は、手書きのエンディングノートをつくるため。2回目は、そこで気づいた課題を解決するために、オンラインのエンディングノートを開発するプロジェクトでした。ダンクソフトに協働を依頼したのは、2回目のプロジェクトからです。
北川 2回あわせて延べ367名の人たちから638万600円の募金が集まりました。「場づくり」のための最初の一歩としても、それなりの成果を得られたと思っています。
┃親も交えた「開かれた場」で対話。プロジェクトが楽しく新鮮だった。
和田 最初は手書きのノートを使っていました。ただ、これにはいくつかの課題がありました。親御さんたちがどう書いてよいかわからないとか、思いついた時に書けないとか、「書く」ことに対するハードルが意外に高いことが分かりました。また、内容が重いので、一人で書いていると苦しく筆が止まってしまうこともあるんです。そこで、ワークショップを実施して、みんなで集まって対話しながら書くことが大事だという気づきがありました。そこで、デジタルをうまく活用して、より負担なく楽しくエンディングノートに取り組む方法を検討したくて、私たちの頭の中で思い浮かんだのが、星野さんの顔でした(笑)。
北川 インターミディエイターとして、開かれた対話を重視して、場づくりの意義もご理解されている星野さんなら、私たちの想いをいちから説明しなくてもくみ取っていただけると思ったことも、大きな理由ですね。
星野 ダンクソフトにご依頼があって、実際にプロジェクトが動き始めたのが2024年の12月末でした。プロジェクトはすべて、今日のようにオンラインのミーティングで行いました。ダンクソフトからは、私に加えて、徳島のメンバーなど何人かが参加しました。確か翌2025年1月くらいには当事者である親の方も交えたダイアログが実施できましたね。
和田 あのダイアログは印象的でした。支援する側・される側という枠を超えて、親御さんもダンクさんもいぶきのスタッフも一緒に、いろいろな立場の人たちが思い思いの意見を交える場になりました。“わちゃわちゃ”という表現がふさわしいのかどうかはわかりませんが、とても楽しく開かれた対話の場がつくれましたね。
星野 私も楽しかったですよ。当事者である親の人たちと直接話し合い、想いを聞くこともできました。そのあと、日本福祉大学の教員の方と学生さんを交えたダイアログも行いましたね。
北川 私たちは最初、関係者だけの閉じた空間でつくっていくものと考えていたんです。それが、多様なアクターを交えて、開かれたプロセスにできたのは、星野さんをはじめとしてダンクの皆さんと連携できたからですね。新鮮でした。
星野 他にも、このプロジェクトでユニークだと思うのは、これらのダイアログやミーティングなど、プロセスをすべて録画しています。それをYouTubeで、メンバー限定で公開をしています。私としては、今回のプロジェクトでは、オンラインでエンディングノートに関する情報を公開するだけでなく、これらの録画や開発履歴など「プロセス」も含めて成果物として提供させていただいたんです。後々、あの時何を言ったかなと、ダイアログなどを振り返ることもできますし、次のプロジェクトに活かすこともできます。親たちが実際に語った映像も含めてアーカイブすれば、子どもたちに親の思いや肉声を残すこともできますよね。
株式会社ダンクソフト 代表取締役 星野晃一郎
また、私が今回のプロジェクトでもう一つ意識したことがありました。それは、最近のデジタル技術の便利さ、快適さをみんなに体感してもらうことでした。たとえば、オンラインのミーティングでは、参加者が話した言葉をAIによって自動で文字起こしができるようになっています。加えて、リアルタイムにダンクソフトのスタッフが、皆さんが話したことを議事録にまとめていくテクニックも見ていただきました。
和田 それだけ中身が濃かったにもかかわらず、今回の開発は速かったですよね。
星野 実質かかった期間は1か月ほどだったと思います。異例のスピードです(笑)。このような利用者へのヒアリングを含めたプロセスは、おそらく一般的には半年くらいかかるのではないでしょうか。
和田 果たして期日どおりに完成するのか、密かにハラハラしていたのですが(笑)。
星野 リモートでの開発環境をフルに活用したことは、スピーディにプロジェクトが進んだ理由のひとつですね。もちろん、生成AIを駆使した要件の整理、ノートの基本フォーマットなど、ダンクソフトのメンバーたちの知見やスキルも活かされています。先ほど北川さんが話されたように、開かれた対話の場づくりが重要だと、あらかじめお互いに共通の認識があったので、プロジェクトを深めるためにより多くの時間を使えたことも大きかったと思いますね。
┃みんなで取り組んでいくコミュニティをつくっていくことが、次のステップ
星野 このオンライン・エンディングノートは、ダンクソフトのクラウドサービス「WeARee!(ウィアリー!)」を活用した仕組みです。最近はスタンプラリーの機能を使った事例を公開しましたが、今回は簡単にウェブページを作成・共有できる機能を活用しました。ウェブページでは、エンディングノートの書き方などの役立つ情報や、作成をサポートするテンプレートをダウンロードできます。今後、コミュニティに集う人たちがダイアログや学習会などを実施する際には、そのイベント情報を掲載したり、コメントを寄せ合ったりすることもできるようになっています。
和田 現在は、いぶき福祉会の親さんとともに、試験的に実施しているステップです。実際には、私たちが親さんたちをサポートしながらエンディングノートをつくります。記載するためのヒアリングを兼ねた対話を行っていきますので、エンディングノートは、よい対話のきっかけとなりますね。必要があればさらに改善を行い、ゆくゆくは岐阜から全国へ、各地の団体でも活用してもらえるようにしていくつもりです。
北川 社会課題として発信していこうという目標を考えるならば、まだまだ今は最初のステップだと感じています。私としては、ツールだけでなく、そこに込められた考え方を広く社会に伝えていきたいと考えています。引きこもりや発達障害の人など、生きづらさを抱えている人はたくさんいます。「障害」という枠組みをはずして、そういう人たちの問題にみんなで取り組んでいく場をつくっていくことが、次のステップだと考えています。
┃多様な人々の力を最大限に引き出すためにも、デジタルは欠かせない
星野 このエンディングノートに限らず、デジタルが寄与できる課題がありそうですね。
いぶき福祉会 事務長/協働責任者 和田善行さん
和田 そうですね。いぶき福祉会では、職員間のオンライン・ミーティングやビジネス・チャットなど進んでいるところもありますが、改善していくことも多いと思います。たとえば勤怠管理などは、昔ながらの判子を使ったやり方だったりします。
星野 いぶき福祉会の事務所に行く度に感じるのが書類の多さですね(笑)。「ペーパーレス」を進めることによって、判子のいらない「サインレス」、さらには「キャッシュレス」を実現できますよ。事務所などの物理的なスペースが空くことによって、その場をコミュニティづくりなどにも活用できます。これをダンクソフトでは、「スマートオフィス」と呼んで推進しています。事務所の真ん中にコピーの複合機があるようでは、まだまだですね(笑)。いぶきのオフィスも、スマートオフィスにしていきませんか。
北川 私たちは拠点が複数あって、お互いに離れているので、施設間を結ぶためのZoom活用は、コロナ禍以前から取り組んでいました。それができていたので、コロナ禍では、ジャムづくりの工房や、新しくできたグループホームをライブ中継して、オンラインで岐阜のいぶきに遊びに来たように感じていただくイベントを実施したりしてきました。先ほどからコミュニティのことが話題に出ていますが、いぶき福祉会には、1000人を超える支援者の皆さんとのネットワークがあります。こうしたコミュニティづくりでも、デジタルでよりよくできますよね。
星野 今回のエンディングノートで利用した「WeARee !(ウィアリー)」にしても、すでにいぶき福祉会で利用していただいている事務局運営に効く「ダンクソフト・バザールバザール」にしても、コミュニティづくりで活用できる機能が豊富にありますので、ご一緒に上手な活用を考えていきたいですね。
和田 福祉の現場では、これから人手不足がますます深刻な問題になってくるという課題もあり、デジタルがそれを補完する未来もありますよね。
星野 私の家庭でも、離れた場所にいる高齢の家族を見守るために遠隔操作できる家電やカメラを使っていました。さほど予算もかからず、すでに活用できるデジタル技術は揃っています。人手不足になる現場をサポートするテクノロジーとして、いぶきさんでも活用できるのではないかな。あとは、いかに人の心に寄り添える仕組みをつくっていくかですね。
北川 そうですね。福祉の現場では、最後は“人の手”が残るんですよね。機械の工場のようにスタッフの均質化をはかってレベルを維持することも大事かもしれませんが、最後は、やはり多様な人々の力ですね。「障害者」といっても、誰ひとり同じ人はいなくて多様です。ですので、その多様な仲間たちを支えるためには、現場で接する人たちも多様であることが重要です。また、人として頼られることが大事だと考えていて、人の力を最大限に引き出すためにも、デジタル技術は欠かせませんよね。
星野 これからは「人間・機械・自然との協働」がますます重要になりますので、人とデジタルのうまい協働は必須になりますね。近年では、厚生労働省でも福祉現場のDX推進に力を入れ始めているようです。エンディングノートと同じように、いぶき福祉会を起点に、福祉業界の中での有効なデジタル活用を社会へと発信していくタイミングが来ているのではないでしょうか。
┃仲間たちとの喜怒哀楽を、広く社会に伝えていきたい
北川 ところで話題は変わりますが、星野さんはコミュニティ・ラジオに長く携わり、生放送の番組もやっていますよね。
星野 はい。中央FMのことですね。中央区のコミュニティ・ラジオなんですが、今はここダンクソフトの本社を、ラジオのスタジオとして使えるようになり、千代田区から放送しているんですよね。
北川 ひとつ相談があります。最近、いぶき福祉会でも「stand.fm(スタンドFM)」を利用して音声配信を始めたのですが、なかなか難しくて……。そもそもは仲間たちの日常や作業所での風景を価値化して社会に伝えられないかと思って始めたのですが。会話や笑い、作業の様子などの「音」に魅力があると思っているんです。それを私が録音して編集しています。
和田 音声で残すことは仲間たちにも好評で、みんなで聞き返すことで新しいコミュニケーションが生まれたりしています。
北川 ところが録音した音声をラジオ用に編集するのがすごくたいへんで(笑)、そこがボトルネックとなっていまして...。
星野 その苦労はわかります(笑)。私が中央FMの番組を生放送にしているのは、面倒な編集を省略するためでもあるんですね。いずれにしてもアーカイブとしても大切なものになるはずなので、あまり加工に手間をかけずにどんどんチャレンジした方がよいと思いますね。
今日、お二人と話をしていて改めて強く感じたのですが、福祉の現場にはデジタルの力によって、よりよい環境をつくり、障害のある仲間の可能性も、スタッフの皆さんの可能性もさらに引き出せるのではないかと感じています。プロジェクトやイベントでのデジタル活用ももちろんですが、日ごろの業務プロセスをデジタルを使って進めていくと、時間を創出することができます。するとその分、大事な支援やコミュニティづくりに、もっと時間と人手を活かせるようになりますよ。人が足りないからこそ、デジタルの出番というわけです。いぶき福祉会とはこれからも一緒に多様な協働をしていきたいですね。全国に先駆けたモデルケースを、一緒に創れるぐらい、やってみたいですね。
和田 こちらこそ、今日はとても楽しく、そして貴重な時間を共有できたと思います。星野さんの話を聞いていて、いぶき福祉会はもちろん、自分の中のデジタル化の知識を、もっとバージョンアップさせていきたいと感じました。
北川 いまのラジオの話もそうなのですが、昔から、日常の中で仲間たちと一緒に感じる喜怒哀楽すべてが価値あるものであり、どうしたら上手く社会に伝えていけるのだろうかと考えています。いぶき福祉会では、30周年を機にミッション・ビジョン・フィロソフィーを刷新しました。活動のどれもが、新しいビジョンである「ケアを文化に」を実現するために、かけがえのないシーンになります。まだまだ語り切れていないことがたくさんあるのですが、ダンクソフトとはこれからも一緒に歩みながら、未来に向けて大きな物語を描いていきたいですね。
星野 その気持ちは私も同じです。では、次回はダンクのラジオ番組にゲスト出演いただいて、この続きを語り合いたいですね。またお話ししていきましょう!