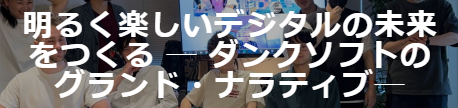7月から、ダンクソフトの新しい年度(43期)がスタートしました。そこで、3人のマネージャーが集まり、代表である星野も交えて、前年度の振り返りと新年度への想いを語り合いました。ダンクソフトの「グランド・ナラティブ(大きな物語=ビジョン)」の実現に向けて、新しい章の始まりです!
┃試練の時期を乗り越え、若手がものすごいスピードで成長した
ダンクソフト 代表 星野 晃一郎
星野 7月、ダンクソフトは新しい年度(43期)を迎えました。お客様をはじめ、ダンクソフトとかかわりを持つ皆様に御礼申し上げます。当社は昨年度から、新しく3人のマネージャー体制になりました。今回よい機会ですので、3人とともに、昨年度の振り返りと新年度に向けた想いを語ってみます。では、まず昨年度の振り返りから。古くからいたメンバーの多くが離れ、ダンクソフトにとって変化が多く、厳しい1年でもありました。いかがでしたか?
竹内 星野さんの言うとおり、人的リソースが減った結果、特に前半はとても忙しい時期が続いたように思います。新しい年度がスタートした現在は、それがようやく一段落した状況でしょうか。
多田 Webチームも、お客様のシステム環境の変更などがあり、みんな忙しい1年でした。
澤口 昔からのメンバーが離れた一方で、新しいメンバーたちが加わり、新陳代謝となりました。その意味でも、ダンクソフトにとって変化の大きな1年でした。この変化をとてもポジティブにとらえています。
星野 では昨年度を経て、ダンクソフトはどのように進化したと感じていますか?
左:開発チーム マネージャー 澤口 泰丞
右:シニアマネージャー 竹内 祐介
澤口 いま「進化」とありましたが、開発チームでいうなら、若手だったメンバーがものすごい勢いで成長したことでしょうか。
竹内 それは私も感じています。ある意味、とてもチャレンジングな状況を乗り越えることで、ふだんの3倍くらいのスピードで成長をとげたような感じですよね。これは若手だけに限ったことではなく、スタッフ全員が一段も二段もレベルが上がったはずですね(笑)
多田 それはWebチームも同じですね。若手たちの成長にはびっくりしています。また、これはメンバーの誰にもいえることですが、仕事へのマインドが変わってきたことも、今までにない成長です。以前は、“指示待ち”をする姿勢が、よくありました。それが、「こうしたらどうですか?」と前向きな提案が出るようになってきました。すごくいい傾向です。
星野 大きな進歩ですね。“小さな提案”ができるようになるチームを数年前から目指してCo-learning(共同学習)の機会をつくってきましたので、見える形で成果を感じられるのは嬉しいことですね。それぞれに試練を乗り越えたからこそ、新しい境地が見えてきたのだと思います。この結果、お客様へ、さらによい価値を提供できるチームになったことは、とても喜ばしいことですね。
┃「ポリバレント」こそ、ダンクソフトで働く醍醐味だと実感した
星野 ダンクソフトでは、以前から「ポリバレント」という考えを大切にしています。これは、一人が固定的な役割で終わるのではなく、状況に応じていくつもの役割ができるようになるという意味で、サッカー用語としても知られています。この真価が発揮された年になりましたね。
多田 それは私も感じました。Webチームでは、これまで各メンバーがそれぞれ専門とする仕事だけを黙々とこなしているような感じがありました。それが、みんな自ら進んで他の業務もフォローするようになりました。昨年度は、私にとってマネージャー1年目という時期だったのですが、メンバーたちにほんとうに助けられたと思っています。
開発チームを見ていても、若手メンバーがプライバシー・マーク業務を担ったり、プログラミング以外のプロジェクトにも率先して参加しているのを見ると、メンバーたちのポリバレント性が発揮されていますよね?
澤口 そうですね。昨年度は、チームの枠組みを飛び越えて、開発チームのメンバーがWebチームの業務をサポートするようなことも多くありました。かつてならまずなかったことで、これもポリバレント現象の一つだと思いますね。ただ私の場合、ふだんからそういうことは意識せずに行っています。ダンクソフトはそういう会社なのだからと。
竹内 澤口さんの言うとおり、仕事におけるポリバレントについては、もう当たり前のようになってきていますよね。これこそが、ダンクソフトでエンジニアとして働く醍醐味だと常日頃から思っています。一般的には、エンジニアであればプログラミングばかりを業務にします。ダンクソフトでは、全社業務やイベント・サポート、お客様との対話なども含めて、エンジニアの仕事ですから、必然的に一人ひとりの幅と役割が広がりますね。
┃コミュニティとの関係づくりから、ビジネスの芽が育ってきた
澤口 昨年度でいえば、お客様との関係づくりを意識したことも新しいチャレンジだったと思います。お客様に、ダンクソフトが考えていることをお話ししたり、逆にお客様が感じていることを語ってもらったり、軽い雑談だけで終わらせるのではなく、文字通り対話を深め、そこから次にできることを模索した1年でした。
竹内 印象的だったのは「やさしいまちづくり総合研究所」様とのプロジェクトですね。そもそもは「インターミディエイター」の活動が縁で始まった協働ですが、ダンクソフトの考え方に共感してもらい、地域づくり・人づくりの中でのデジタル活用を一緒に模索していける兆しがあります。もう一つあげるなら、徳島県のある病院で進めている案件です。これは私が趣味にしているマラソンを通じて、中学校時代の同級生に再会したことがきっかけで始まったプロジェクトです。
多田 「インターミディエイター」については、私をはじめWebチームのメンバーたちも学んでおり、それがお客様との関係づくりに役立っている実感がありますね。新年度は、もっとお客様と対話する機会を増やして、相互に“良い関係”をつくりたいと考えています。
竹内 いいですね!社内でも輪が広がっていますね。昨年度は、コミュニティとのつながりから新しいビジネスを生み出していくという、ダンクソフトならではの「関係づくりマーケティング」が花開き始めたような感触があります。星野さんが関わっている「神田藍の会」がよい例ですね。
星野 お客様との関係づくりに関しては、実際、お客様側からも高い評価をいただいていますし、着実に成果に結びついています。ポリバレントのことも含め、開発もWebも、新設したマーケティング・チームも、チームとして大きく成長したとみています。先日別の会議で、神田藍のプロジェクトに関わっているメンバーが、その価値を語ってくれ、私としても手ごたえを感じています。「地域づくりと関係づくりの未来」に寄与していくことは、ダンクソフトのグランド・ナラティブ(ビジョン)にも含めていますので、引き続き社内外の皆さんとともに推進していきましょう。
┃お客様との共感から、ダンクソフトらしい協働を始める
竹内 今年度については、新しいお客様とどうつながれるかを一番のテーマにしたいと思っています。先ほど話した、地域コミュニティとの関係づくりをベースにしたスタイルをもっと模索してみたいと考えています。私は現在、和歌山県田辺市の大塔中学で、プログラミング授業の講師をしています。阿南工業高等専門学校では長く講師をつとめていますが、中学生は初めてで、結構頑張って下準備をしているんですよ(笑)。このような取り組みも、何かのきっかけになればと考えています。
澤口 私も、先ほど話したように、お客様との関係づくりに力を入れていきたいですね。これから出会うお客様に対しては、ダンクソフトの考え方や取り組みを機会あるごとに紹介していき、共感していただける方々と出会いたいですね。また、既存のお客様では、課題や困りごとに耳を傾け、ただデジタルをどう使うかを超えて、どんな未来を描いていくのかといった対話を、もっと増やしていこうと考えています。
多田 それはとても未来志向ですね! 私たちWebチームとしては、新メンバーの採用も含め、まずチーム力の強化がテーマです。よりいいチームになり、お客様と実施するプロジェクトの質をさらに高めていくためのチームづくりを今年度に始める予定です。メンバーたちの学びあいの機会を増やし、みんなでさらにレベルアップしていきたいですね。
星野 新年度に向けたトピックを一つ紹介すると、ダンクソフトの本社オフィスの一角をリニューアルしました。コミュニティ活動として取り組んでいる、コミュニティFM「中央エフエム」のスタジオ機能を強化するために、専門の放送機材を設置しています。ダンクソフトではこれを「スマート・オフィス・コミュニティ」と呼んでいます。オフィスのペーパーレス・サインレス・キャッシュレスを実現することで、仕事だけでなく、スペースを有効活用してコミュニティ活動のために使用できる空間をつくることができます。ここにいくつものコミュニティが、かわるがわる集ったり、交流したりすることが始まっています。例えば「神田藍の会」の催しや、ラジオの放送など、このスペースをリアルなコミュニケーションの場としても活用していこうと考えています。
┃「グランド・ナラティブ」(ビジョン)の実現に向けて、新しい関係づくりを
竹内 いまお話にあった社外活動とともに、社内の取り組みとしては、メンバーたちのコミュニケーションをさらに活性化させたいですね。全社的なミーティングである「DNAセミナー」を何人かのメンバーが自主的に企画してくれたり、メンバー全員参加の「全社会議」が定期的に開催されるようになったりと、昨年度はいくつかのよい兆しがありました。それをさらに進化させて、新しい働き方を追求するダンクソフトならではの、よい文化をつくっていきたいと考えています。
澤口 以前から実現したいことの一つですが、リアルで対話する機会を増やしていきたい。ダンクソフトはコロナ禍があけても、全員がリモート勤務が基本なので、チームが違うとなかなか会話する機会がないんです。月1くらいのペースで出社できる日を設けたりすると、リアルに集う機会ができます。雑談したり一緒に食事したりする機会が生まれ、それ以外の時間でのコミュニケーションも円滑になると考えています。
多田 Webチームでは、これは以前からの雰囲気なのですけど、仕事中の雑談は「時間のムダ」みたいな空気があるんです。お客様を大切にする心からそうなるのですが、ただ、雑談の中から新しいアイディアや次の展開が生まれることもあります。雑談のプラス効果ですね。このあたりの感じも、チーム同士の交流が活発になれば変化してくるはずです。コミュニケーションの活性化は、今年度の一番のテーマだと思います。
星野 3人の話を聞いていると、お客様へも、社内のメンバー同士も、改めて「コミュニケーション」が大事なキーワードになりますね。コミュニケーションには、「雑談・会話・対話」が含まれます。この3つをうまく織り交ぜながら、新しいことを創造する「対話の文化」を、さらに育てていきたいですね。
新年度のトピックをもう一つ紹介すると、この7月に滋賀県に行き、地元の福祉団体の方々とデジタル化に向けたヒアリングを行います。私の個人的な経験からも、高齢者福祉の現場で、もっとデジタルがうまく活かされると、介護がもっと楽になる実感があります。デジタルがここにどんな貢献ができるか、今から楽しみです。私だけでなく、ますます頼もしくなる3人のマネージャーたちにも、お困りのことがあれば、あるいは、どうやって新しい未来を創ろうかというときには、どうぞお気軽にご相談ください。
ダンクソフトが描く「グランド・ナラティブ(大きな物語=ビジョン)」では、今日話題になったお客様やコミュニティとの関係づくりの未来、そしてスタッフが学びあう環境を充実して将来的にはテック・スクールのようなダンクソフトになろうという未来を含め、4つの未来像を掲げています。お客様やパートナー、地域コミュニティ、そして、それぞれの特色あるコミュニティを持つ皆様とともに、今年度もダンクソフトらしいチャレンジを続けていきます。